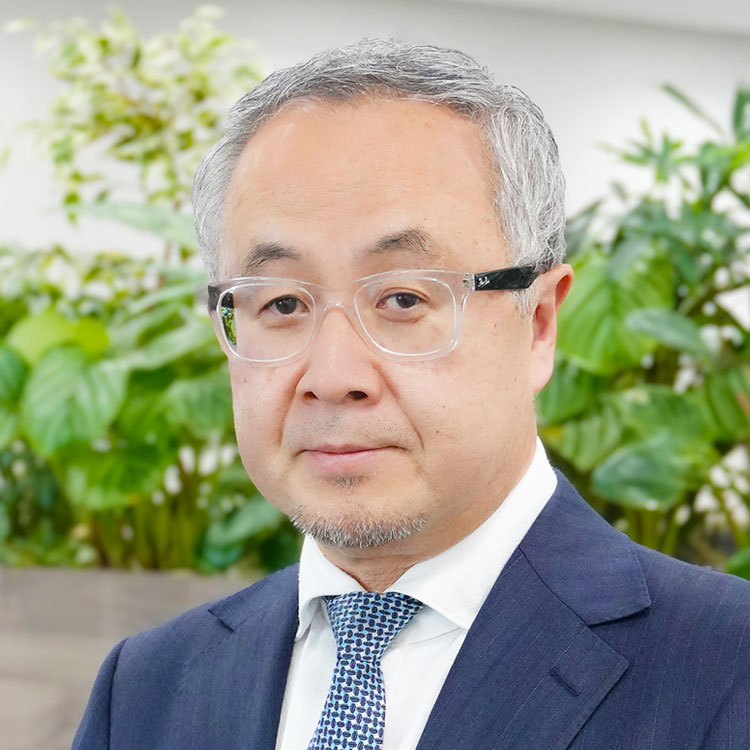渋谷駅周辺の大規模再開発が「100年に一度」と言われるのは、超高層ビルが何棟も建設されるからではない。官民が協力しながら、駅を動かし、川の流れを変え、新たな歩行者ネットワークをつくりあげることを通じて、まったく新しいまちに生まれ変わらせるという試みだからだ。しかもそれを巨大ターミナルの機能を維持しつつ実現するという点でも例がない。パシフィックコンサルタンツはこのプロジェクトに初期の検討段階から関わり、現在も支え続けている。その中心で長く携わった小脇立二、久保寿、丹羽隆泰、並木嘉男、紙野輝恵の5人に話を聞いた。
渋谷プロジェクトとは
渋谷駅周辺の駅まち再構築を目指した官民連携の大規模プロジェクト。2000年に決定した東急東横線と地下鉄副都心線の相互直通運転と東横線渋谷駅の地下化がきっかけとなり、渋谷駅周辺が抱える多くの課題を解決して渋谷の魅力向上を図ることが目指された。具体的には「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」「渋谷駅周辺まちづくりビジョン2016」を上位計画として、渋谷駅街区の土地区画整理事業・鉄道改良事業・国道拡幅事業等の基盤整備事業と5つの街区※を中心にしたさまざまな開発事業が連動して進められている。すでに多くの複合ビルや商業施設が開業。2027年度中(2028年3月)の渋谷スクランブルスクエア第Ⅱ期(中央棟・西棟)の竣工で、渋谷ヒカリエで幕を上げたプロジェクトは最初の区切りを迎える。
※ 5つの街区
東急文化会館跡地を核とする「渋谷ヒカリエ」/東急東横線渋谷駅跡地などの「渋谷ストリーム」 /旧東急東横店跡地や渋谷駅ビルなどの「渋谷スクランブルスクエア」/旧東急プラザ跡地を中心とする「渋谷フクラス」/渋谷駅桜丘地区の市街地再開発事業である「渋谷サクラステージ」
INDEX
川を動かし、まちに組み込む――大改造ポイント③ 川沿いの遊歩道の新設と線形変更
谷を格子状につなぐ新たな歩行者ネットワークの創造、JR、銀座線の渋谷駅の移設に続く渋谷大改造の3つめのポイントは渋谷川の扱いだった。
渋谷川は新宿御苑を水源に、渋谷区・港区内を通って東京湾に流れ込む全長約10㎞の二級河川だ。しかし、急速な都市化と下水道普及のなかで、1960年代には旧宮益橋から上流の区域を暗渠化して下水道幹線として使用することが決定。工事は急ピッチで進み、1964年には下水道「千駄ヶ谷幹線」として整備が完了した。一方、旧宮益橋から下流の渋谷駅方向は川のままだったが、東急東横店の地下に蓋をした状態で抱き込まれ、それが駅前を過ぎたあたりから再び地上に顔を出し、ビルの間を天現寺方面に流れていた。


再び地上に出た渋谷川は「臭い、汚い、暗い」と評される"邪魔者"だった。実際、開発の関係者からは蓋をしようという声が上がっていた。しかし、高度経済成長を背景にしたやや強引とも言える暗渠化は時代にそぐわない。行政も「暗渠化して遠ざけるより親水機能を持たせて共存する」という基本姿勢に転換していた。そこで検討されたのが、二層式河川方式よる整備だった。河道を上下2段に分け、下に治水機能を持たせた河川、上は流量を抑えて親水機能を持たせた遊歩道とするものだ。しかし、河川管理者の東京都は首を縦に振らなかった。「二層河川としても河川に蓋をして本来の河川が見えなくなり、河川空間をなくすことはできない」ということであった。これに対して、河川のままで、河道を少し広げて遊歩道等を整備して憩いの場を作ろうという代案を考えた。今度は日常の河川管理をしている渋谷区が、「渋谷川はいったん豪雨に見舞われれば短時間で水位が上がる。急激な増水時に河川内の人を逃がすことが難しいので、河道に人を入れることはできない」というのだ。
「そこで検討したのが流れをきれいにしながら川を残し、その脇に遊歩道や広場を設けて水の流れを眺めながら散策したり、休息できるようにするものでした」と小脇。管理者もそれならと同意、設計事務所が新たに計画する高層ビルの脇に、渋谷川に沿って続く600mの遊歩道を計画した。護岸の傾斜もやや緩くし、そこに滝のように水を落とす「壁泉」も採用。蓋をするのではなく見て楽しむものへと180度転換した。
しかし、渋谷川にはもう一つ問題があった。それは旧宮益橋から再び地上に顔を出すまでの駅の東口地下を流れる部分の対策だった。駅前は地下鉄とJRの乗り換え動線であり、バスの乗降機能もある。人が滞留できる地下広場も含めた快適なアーバン・コアが必要だった。ところが従来の流路は駅に近く、計画の妨げになるため駅から離すことが必要だった。 しかし曲げれば抵抗が生まれ、スムーズに流れなくなる可能性がある。しかも、渋谷川の地下部分の管理は、従来の河川から下水道の扱いに切り替えることになっていたから、下水道の基準を満たす断面形状と線形でなければならなかった。「どこまで線形が変えられるのか、河川部に声を掛けました」と小脇。社内に河川の専門技術者がいること、そして、当社のつくば技術研究センターには大規模な水理実験施設もあることを小脇は改めて心強く思ったという。話を聞いた河川部流域計画室の並木嘉男は、曲げることの影響は決して小さくないことから、基準を満たす水の流れについては模型実験での確認が欠かせないと考えた。自身もつくば技術研究センターで勤務した経験があり、センターには下水道部門の経験を持つ同僚もいた。「早速20分の1の模型をつくり、水を流して検証しました」と並木。
当初の線形案を再現すると計画流量が流せない可能性があることがわかり、変更が必要になった。地下空間の利用計画との兼ね合いもある。試行錯誤が続き、その後つくり直した模型は何十という数に上ったという。開発事業者や行政担当者の立ち会いのもとで、この線形で進めようという結論を得たのは、実験の開始から3年以上の月日が経過していた。
道路内の建築物を計画する
谷地形や交錯する鉄道・道路を克服する3次元の格子状ネットワーク、駅の大胆な移動、川の活用と線形変更――渋谷大改造はこの3つをベースに、同時に5つの街区で超高層を含むビルの建設が計画されていた。このすべてをどうつなぐのか、個別の施設の外で道路内に設けられる通路や広場の計画は大改造が進むまちを有機的に一体化するために欠かせない重要な、そして最後のピースだった。実際、建物側がここに入り口を設けたいと考える場所は、近隣の他の建物やまち全体から見て、ずれたものになっていることがしばしばだった。しかし駅や建物を快適につなぐ通路や広場がなければ、渋谷大改造は完成しない。その役割を担ったのがパシフィックコンサルタンツの建築部からこのプロジェクトに加わった紙野輝恵だった。「2009年の都市計画の決定の少し前くらいから、小脇さんが珍しく悩んでいるので、声をかけたのをきっかけに、渋谷プロジェクトに参加しました。渋谷ヒカリエが着工し、駅の移設も具体的になり始め、5つの街区では再開発計画が動き始めていました。各街区のプロジェクトについて情報を得て、それを重ね合わせていかにつなぐかという検討を行いました。道路内の通路や広場などの建築物はまちづくり全体を見ているパシフィックコンサルタンツの重要な仕事の1つでした」と紙野。内藤廣建築設計事務所と共同で計画・設計した渋谷駅東口と渋谷ヒカリエをつなぐ全長55mの跨道橋「渋谷駅街区東口2階デッキ」もその1つだった。
「道路の上を通すものですから、道路管理者はもちろん警察や消防をはじめとする多くの関係者との協議が必要です。特に安全性、機能性は重要で、通常の跨道橋は大きくても幅員は6m程度ですが、ここでは大量の人が流れることを想定して8m幅を確保しました。また、単なる道路横断の機能だけでなく新しい渋谷のランドマークの1つになるものですから、デザイン面にも配慮しました」

実際にこの跨道橋は2012年度のグッドデザイン賞を受賞。審査員からは「構造的な工夫に始まり、カーテンウォールのディテール、素材や照明など、綿密にデザインし尽くすことで、今までの跨道橋には無い軽快さと透明性が実現されている。跨道橋がデザインの領域に入ってきたこと自体も喜ばしい。公共空間のデザインのあるべき姿を示すものとして高く評価したい」という講評も得た。
他に紙野が担ったものに東口地下広場がある。相互乗り入れをする東横線と地下鉄の渋谷駅や渋谷ヒカリエとJRをつなぐ乗り換え動線であり、東口のアーバン・コアを形づくるもので「渋谷大改造」の中の重要な結節点の1つとなるものだ。ただし、地下空間には新たに下水道として管理される渋谷川が流れ、さらにその下には水害対策の1つとして、4,000トンの容量をもつ巨大な雨水貯槽も設けられることになっていた。地下広場は川と貯水槽の間に拡がる空間につくることになり、内部には大きな段差を抱え込むなど、広場とするには条件が厳しかった。しかし、単なる乗り換え移動ではなく、歩いて楽しい歩行者空間であり、広場にしたいと紙野は考えていた。さらに計画の途中でここに店舗を構えるという要請が加わった。
「渋谷再開発は当初から住民が積極的に参加して計画を進め、完成後の運営にも地域の参加が重視されています。東口地下広場も、店舗を出したり広告スペースを確保して収益を上げ、それを運営に活かし官民で盛り上げていくというエリアマネジメントを重視していて、店舗スペースを確保することになりました。ただし、商業施設ではありませんから、その設定はありません。設計変更を繰り返して店舗スペースを確保し、また費用の負担のしかたにも関係することから、公共側の工事とエリアマネジメント側の工事をどう分けるかといった検討も進めました。複雑な計画・設計になりましたが、これも渋谷プロジェクトならではの取り組みだったと思います」

来訪者にはその日が完成形であること
渋谷大改造は、計画はもちろんその施工についても大きなチャレンジを伴うものだった。工事の種類は多岐にわたり、その範囲も広く、しかもほぼ同時に進行する。着工の順番や資材置き場の確保、工事車両の動かし方、安全な仮設通路の確保などについて細部にわたる調整が必要だった。その支援もパシフィックコンサルタンツの重要な役割だった。 どこの工事を先行すべきか、ある工事が終わったときに隣はどういう状況にあるのか、1つの工事が遅れただけでも、影響は全体に及ぶ。常に状況を掌握し、工事の進捗管理を進めなければならない。特に神経を使わなければならなかったのは長期にわたる工事期間中の安全と利便性の確保だった。小脇が語る。
「あるとき、まちづくりの調整会議のメンバーである学識経験者からこう言われました。『まちを訪れる人にとっては、その日の渋谷の姿が完成形であり、きちんと使えるものでなければならない』と。まさにそうです。今は工事中だから仕方がない、という甘えは許されないと、改めて肝に銘じました」
たとえ仮設の迂回路であったとしても、安全はもちろん、できる限り快適なものとして提供しなければならない。それこそが全体調整に関わるものが考えなければならないことだ。まちづくりといえば、デベロッパーが主導し、組織設計事務所やゼネコンの手で進められていくものと思う人が多い。確かに、1つの街区で複合ビルを1棟か2棟整備するのであればそうかもしれない。しかし、そこに鉄道駅や歩行者ネットワーク、駅前広場に代表されるパブリックスペースが加わり、さらに幹線道路や河川も含めて、まちのインフラを最適化・アップデートし一体で大きなまちづくりを進めるのであれば、官民を結びながら全体を俯瞰し、調整する存在が必要になる。それこそが総合力を持つコンサルタントの役割であり、パシフィックコンサルタンツが全力で取り組んできたものだった。
渋谷の未来に想うこと
駅の移設が終わり国道246号の南側に新たな改札ができ、「渋谷ヒカリエ」を皮切りに各街区の建物も続々と竣工し、「渋谷スクランブルスクエアⅡ期」とハチ公広場等の竣工により、「渋谷大改造パート1」は大きな区切りを迎える。その後も宮益坂地区や渋谷二丁目西地区、公園通り西地区での再開発が続き、渋谷区役所やNHK放送センターの建替え計画を含めれば「渋谷大改造パート2」はさらに続くことになる。しかし、「渋谷大改造パート1」の竣工は、当初掲げていた1つのゴールとなる。パシフィックコンサルタンツのメンバーも、それぞれに感慨を胸にしている。
「間違いなく世界から注目される駅まちづくりになっていく」と鉄道関連業務に携わった丹羽は言う。
「地下鉄銀座線ホームは東口の地下広場の上空に設けられましたが、ホームの屋根の上は歩行者デッキとなり、渋谷ヒカリエから渋谷スクランブルスクエアを通って渋谷マークシティまで、渋谷の東と西が空中通路でフラットに結ばれます。こうして駅を組み込んだ新たな歩行者ネットワークの創造や交通広場など、渋谷の駅まち大改造はTODのベストプラクティスとして世界から注目されるものになります。それに関われたことは大きな誇りですし、これから渋谷にどんな人が集い、交流して賑わいを見せてくれるのか、注目していきたいと思っています」
また、従来関わることはなかった駅前開発に河川技術者として加わった並木は、こう語る。
「渋谷ストリームの竣工後に、その建物横に伸びる渋谷川沿いの遊歩道を実際に歩いてきました。渋谷川という河川空間を活かすために河川管理者との仲立ちをしたり、東口の地下部分の線形の結論を得るまでには長い時間がかかったので感慨もひとしおでした。私は現在、首都高速道路の日本橋区間の地下化という大きなプロジェクトに携わり、地下化に伴う日本橋川への影響の検討と地下化後の日本橋川とまちづくりをつなぐための検討を行っています。河道の整備条件や工事中の影響などを水理模型実験で検証したり、河川技術者として河川とまちを融合させるための解析等を行っていますが、渋谷、日本橋と続く『河川×まちづくり』に若手と一緒に取り組み、経験や技術を伝えていくことも私の仕事だと思っています」
建築部の技術者として歩行者デッキや地下広場などの計画・設計に当たると共に、プロジェクト全体の調整にも携わってきた紙野は「まだまだ仕事は終わらない」と表情を引き締める。
「渋谷大改造の取り組みでは、2011年に『渋谷駅中心地区デザイン会議』が組織されています。建築家や学識経験者、行政や地元代表で構成し、渋谷らしさをもった景観形成のためにデザイン調整を行うことが目的です。さまざまな議論をしてきましたが、これこそ議論をしてきた成果だと思ってもらえるように、最後までしっかりと仕事をしていきたいと思っています」
また、小脇と共に初期の段階から渋谷のプロジェクトに関わってきた久保はこう語る。
「駅まち一体の再整備は、コンパクト・プラス・ネットワークの重要性も鑑みると都心だけではなく郊外や地方においても一層重要な取り組みになると考えています。一方で多くの人が行き交う駅前ですので、さまざまなアクティビティが実現し、安全安心であることが欠かせません。その点、パシフィックコンサルタンツは、まちづくり、交通計画、鉄道、道路、河川、上下水、建築、構造、施設、官民連携等などあらゆる分野をカバーする専門家を擁し、社内外のネットワークももっています。渋谷はまさに、当社の全分野の技術者が一致団結したからこそできた全体調整の支援でした。渋谷で得たものをさまざまな場所での駅まち開発やTOD(公共交通指向型開発)に活かし、建設コンサルタントとしての役割を果たしていきたいと思います」
パシフィックコンサルタンツの渋谷プロジェクトのリーダーである小脇は、1997年から渋谷に関わってきた。2027年には丸30年が経過することになる。小脇はこう締め括った。
「渋谷を、世界をリードするまちにつくり上げようという地域住民の皆さんや行政関係者、民間事業体の関係者の熱い想いに触れ、大いに刺激を受けて走り続けた30年です。感謝しかありません。この渋谷プロジェクトに、社内で関わった人は100人以上になると思います。その誰一人として欠かすことはできないし、関わった全員のチームとしての成果だと確信しています。今回のインタビューに参加しているメンバーを含めて、社内のメンバーには本当に恵まれました。相談に行くと『そのことなら、あの部署に詳しい人がいる』と教えられたことは数え切れないほどで、私が訪ねていくとどんなに忙しくても、身を乗り出すようにして話に耳を傾けてくれ、貴重なアドバイスや、時には現場に来て力を発揮してくれました。デベロッパーや鉄道会社は資産を持っていますが、コンサルタントである私たちには、そのような有形の資産はありません。人だけが資産です。その"人"の魅力をこのプロジェクトほど感じさせてくれたものはありませんでした。プロジェクトの中で、ある学識経験者から『あなた方コンサルタントは歯車だ』と言われ、まさにそうだと思いました。「歯車」という言葉にネガティブな意味を感じる人もいますが、私たちが歯車の1つとして正しく役割を果たすことで、すべてが連動して回転し、それが大きな力に統合されて共通の目標を達成することができます」
「渋谷大改造」――それはコンサンルタントの果たすべき役割の大きさと存在価値を改めて示すプロジェクトだったといえるかもしれない。